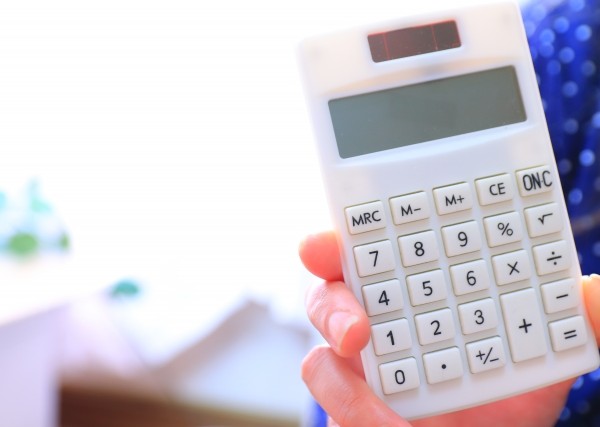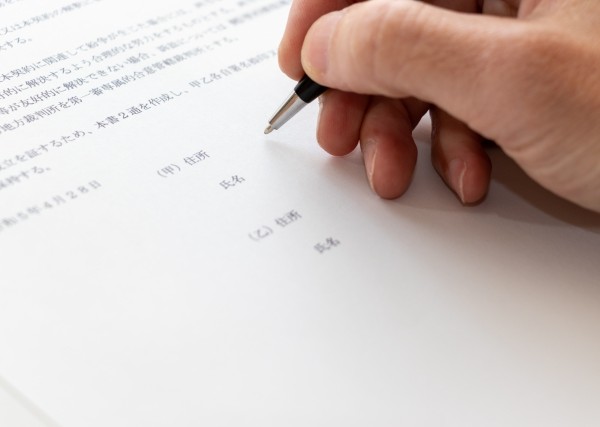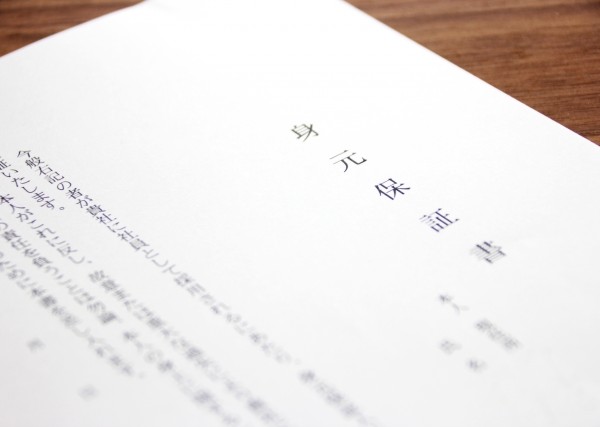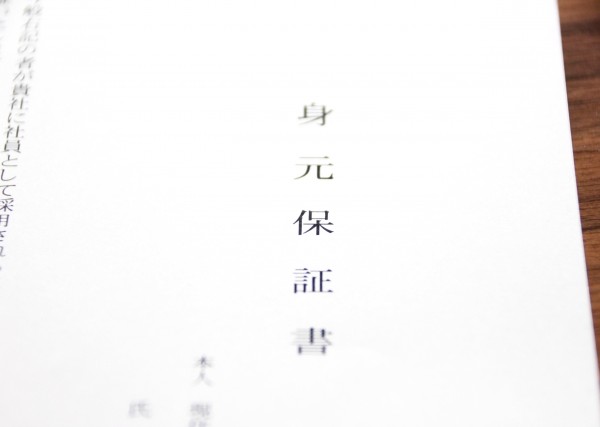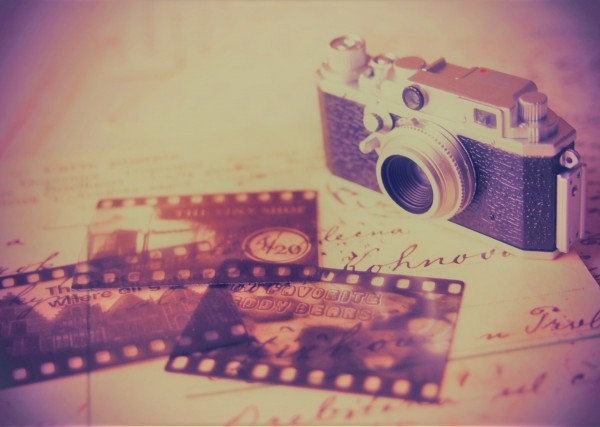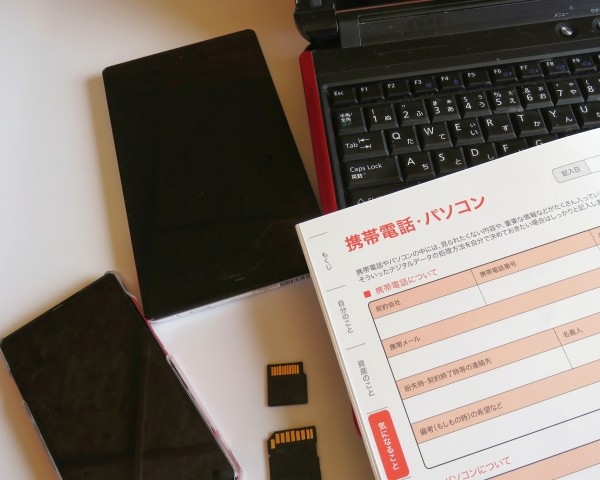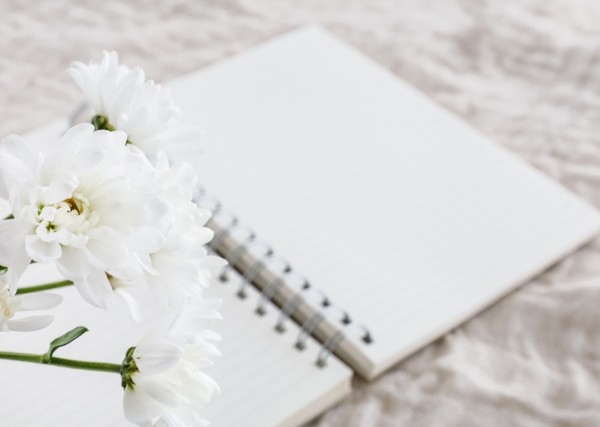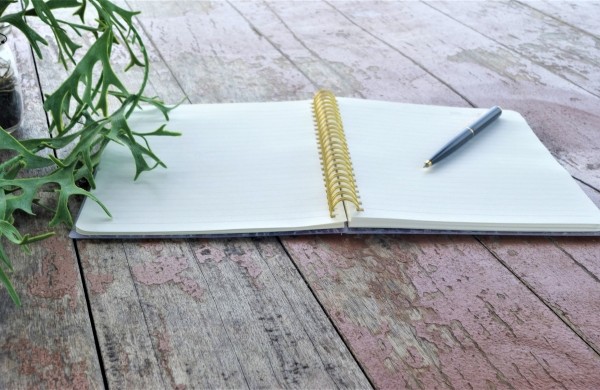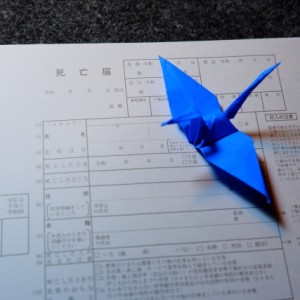宗教と葬式-各宗教の葬儀慣習
こんにちは。この記事では、様々な宗教がどのように葬儀を行っているのか、日本の具体例を交えてご紹介します。それぞれの宗教が持つ独特の儀式や慣習を理解することで、他人の信仰を尊重し、多様な価値観を受け入れる視点が広がるかもしれません。それでは、まずは仏教から見ていきましょう。
仏教の葬儀慣習
日本で最も一般的な葬儀形式は仏教のものでしょう。特に浄土真宗や曹洞宗など、宗派によって儀式の内容は異なりますが、基本的な流れは似ています。
通夜と葬儀
日本の仏教の葬儀では、亡くなった人を偲ぶために「通夜」が行われます。通夜では、亡くなった方の霊前に参列者が順に手を合わせ、お経を唱えます。翌日に行われる葬儀では、さらに詳細な儀式が行われ、最後に遺体を火葬します。
戒名
また、仏教の葬儀では「戒名」を授けるのが一般的です。戒名は、亡くなった人が次の世界へ進む際に名乗る名前で、その人の人生を象徴する言葉を含むことが多いです。
キリスト教の葬儀慣習
キリスト教の葬儀は、仏教の葬儀とはかなり異なります。キリスト教では「復活の希望」を大切にするため、葬儀は故人の死を悲しむ場ではなく、天国への旅立ちを祝福する場とされています。
葬儀とミサ
キリスト教の葬儀では、司祭が故人の生涯を讃える言葉を述べ、参列者全員で賛美歌を歌います。その後、故人のためのミサが行われ、聖書の一節が読まれます。このミサは、故人が神と一体になるための祈りの時間とされています。
埋葬
キリスト教では火葬よりも埋葬が一般的です。これは、キリストの復活の信仰から来ており、故人の体が復活の日に備えて大地に還されると考えられています。
その他の宗教の葬儀慣習
他にもイスラム教、ユダヤ教、シク教など、各宗教ごとに独自の葬儀慣習があります。しかし、これらの宗教は日本では少数派であり、具体的な例を挙げるのは難しいです。
まとめ
仏教、キリスト教をはじめとする各宗教は、それぞれ独自の葬儀慣習を持っています。その慣習を理解し、尊重することで、故人を偲ぶ時間をより深いものにすることができます。多様な宗教文化を理解することは、共生社会を築く一歩とも言えるでしょう。